本日4月1日より、相続が発生した際の決まりごとが変更されます。
もうすでにご存じの方も多いかもしれませんが、何がどのように変更されるのかをご紹介します。
相続登記のルールが変わる
2024年4月より、不動産を取得した相続人は所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)の申請をしなくてはいけず、義務に違反した場合は10万以下の過料が発生するように変更となります。
加えて、2026年4月からは「住所等の変更登記の申請義務化」も施行される。これは、不動産の登記簿上の所有者について、転居等で住所が変更になった場合、変更した日から2年以内に登記申請することを義務化するためのルールです。こちらも相続登記の申請義務化と同様に、違反した場合には5万円以下の過料を支払うことになってしまいます。
所有者不明の不動産を発生させることを防ぐためのルール変更ではあるが、転勤の多い方などは申請手続きの負担が増えてしまうことになるでしょう。
なぜ相続登記申請が義務化されるのか?
なぜこのようなルールへ変更されるのかというと、亡くなった親から実家を受け継いだ場合、これまでは相続登記(名義変更)の申請をする義務はありませんでした。そのため数十年にわたって名義が変更されず、長年放置されたことで実質的な所有者が不明状態になり、処分しようにもできず廃墟となる不動産が全国各地で急速に増えていることが原因であると言われています(実際、国の調査結果を確認すると、保管しているすべての登記簿謄本のうち20%は所有者が分からない不動産だったそうです)
相続登記の申請義務化により起こりそうなトラブルとは?
このルール改正を通して、今後新たに発生しそうなトラブルの代表は、名義変更をしないまま現在まで至った不動産の相続人は、まるでネズミ講のように増えてしまっているということではないでしょうか。この問題が発生するメカニズムはというと、名義を変更しなかった不動産は共有財産として扱われるため、相続の権利を持った人が増え続けてしまうからです。
例えば、曾祖父の代から名義変更されていなかった不動産を相続することになるとすれば、顔を合わせたことがない親族の人たちも相続人としてカウントされる・・・そんなことも起こりえるわけです。
つまり、新たな相続ルールが開始されることにより、自分の孫やひ孫の代に迷惑をかける可能性が出てきたわけです。
相続登記の申請ができない状況ではどうするのか?
とはいっても、兄弟姉妹などとの遺産分割協議がまとまらず、相続する割合などが決まりそうにないケースもあることでしょう。そんな場合には、同じタイミングで施行される「相続人申告登記」の申請をすれば、相続登記申請の義務を果たしたとみなされるようになります。
申請時には、申請者のみの戸籍謄本などを提出すればよいため、相続人全員から公的書類を集める必要もなく申請は簡素化されています。しかし、相続人各自が「相続人申請登記」を行う必要があるので注意が必要です。
そして、相続人申告登記後に遺産分割協議がまとまった際、遺産分割の結果に基づく相続登記を行う必要があります。これは、遺産分割の日から3年以内に登記を行わなければ、同じく過料を支払うことになるので、注意しておきましょう。



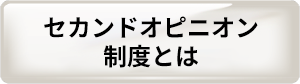
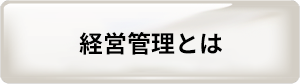
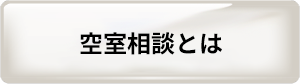

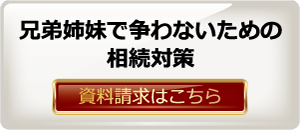
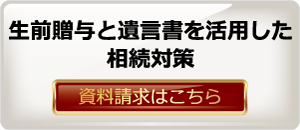
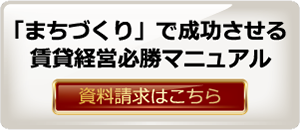
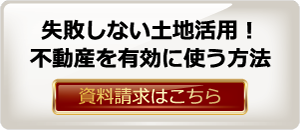




 2024年4月から変更される相続登記の申請義務化とは?
2024年4月から変更される相続登記の申請義務化とは?