賃貸経営で「利益が出たのに手元に残らない…」という悩み
「昨年は家賃収入がかなり増えたのに、残ったお金は思ったより少なかった…」
「節税ってよく聞くけど、何をすればいいのか正直よくわからない」
賃貸経営オーナーの方から、こういった声をよく耳にします。
その原因のひとつが、所得が増えれば増えるほど税率も上がる“累進課税”の存在です。
特に、所得が1,800万円を超えると、最大税率は55%。収入の半分以上が税金として徴収されてしまうこともあります。
こうした状況に対し、税理士の間で注目されているのが「資産管理法人の設立」です。
資産管理法人は、うまく活用すれば大幅な節税が可能になる一方で、注意点や失敗リスクもあります。
資産管理法人とは?
資産管理法人とは、不動産や有価証券といった個人資産を法人名義に移し、法人として管理・運用していくために設立される会社です。
特に賃貸経営者が活用するケースが多く、「節税法人」とも呼ばれることがあります。
個人で得ていた収入を法人に移すことで、法人税制の枠組みを活用し、所得税との税率差や経費の計上範囲の違いを活かした節税が可能となります。
所有型と管理型の違い
-
所有型法人:法人が物件を所有し、家賃収入も法人に入る
-
管理型法人:物件は個人所有のままで、法人は管理業務を受託(管理料収入を得る)
所有型の方が節税効果は大きいですが、不動産を法人に移す際の税負担(譲渡所得税や登録免許税)に注意が必要です。
所得税 vs 法人税|節税になる仕組みを図解
累進課税の壁|高所得者ほど税率が上がる
個人所得には以下のように累進課税が適用されます:
| 課税所得 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
|---|---|---|---|
| 900万円超~1,800万円以下 | 33% | 10% | 43% |
| 1,800万円超 | 45% | 10% | 55% |
一方、法人税の実効税率は 約23〜30% で一定です。
この差を活かすことで、個人で課税されるよりも法人で受けた方が有利になるのです。
法人化の主な税務メリット
-
赤字の繰越控除:最長10年(個人は3年)
-
損益通算の自由度が高い
-
退職金の積立が可能
-
経費計上できる範囲が広がる
法人を使った具体的な節税方法|経費・所得分散の活用術
1. 役員報酬で所得分散+給与所得控除を活用
役員報酬を自分や家族に支払うことで、
-
法人側:報酬は経費として損金算入
-
個人側:給与所得控除を適用
これにより、全体の課税所得を圧縮できます。
2. 社宅や自動車、出張費などの経費化
法人にすることで、以下の支出が経費として認められやすくなります。
-
社宅(賃貸物件の一部を法人契約で社宅扱い)
-
自動車のリース料・保険料
-
出張旅費・日当(視察名目での地方物件調査など)
3. 家族を役員にして報酬を支払い、所得分散
たとえば奥様を非常勤役員として年間103万円以内で報酬を設定すれば、本人の所得税・住民税・社会保険料もゼロで抑えられます。
資産管理法人が向いている人の条件
以下の条件に該当する人は、資産管理法人の設立を検討する価値があります。
-
年収が 1,500万円以上 ある
-
賃貸収入が安定的に入ってくる
-
株式・不動産など運用資産が大きい
-
相続や贈与を意識した資産の承継を考えている
資産管理法人のデメリットと注意点
設立・維持コストが発生する
-
登記費用:約20〜30万円
-
毎年の法人住民税均等割:最低でも7万円
-
顧問税理士や決算書作成費用:年間20〜50万円程度
経費の実態が必要|名ばかり法人はNG
税務調査では、実態のない経費や役員報酬は否認されます。
家族に報酬を出す場合も、出勤簿や議事録などの証拠を残しておくことが必要です。
社会保険加入の可能性あり
常勤役員が1名以上いる場合、社会保険の加入義務が発生します。
思わぬ保険料の負担になるケースもあるため要注意です。
【事例で学ぶ】資産管理法人で得した人・損した人
成功事例:年収2,200万円のオーナーが年間税負担約200万円減
東京都在住の60代男性オーナー(賃貸物件6棟保有、年間所得2,200万円)は、累進課税によって毎年約1,000万円近くの税金を支払っていました。
相談の結果、資産管理法人を設立し、管理型法人として物件の管理業務を法人に委託。法人からの収入は月額80万円。ご本人と奥様に役員報酬を支払い、それぞれの給与所得控除を活用。さらに社宅を法人名義で契約し、年間約200万円の経費削減に成功。
結果として、年間の税負担は約200万円軽減されました。
失敗事例:実態のない役員報酬が否認され、追徴課税+延滞税
一方、別の50代男性オーナーは、節税目的で法人を設立し、家族全員を役員に登記して役員報酬を支払っていましたが、業務実態や出勤記録が一切なく、税務調査で否認。
約3年間で支払った役員報酬のうち、500万円超が不当経費とされ、追徴課税・延滞税で計150万円の追加負担となりました。
「税理士に任せていたので大丈夫だと思っていた」とのことですが、オーナー自身が内容を理解していなかったことが最大の落とし穴でした。
資産管理法人は相続対策にも有効
本コラムの趣旨とはずれてしまいますが。資産管理法人は、相続税の評価圧縮やスムーズな事業承継にも効果的です。
不動産の評価圧縮
法人が不動産を保有する場合、相続税評価額は貸家建付地評価や法人評価の影響で個人所有よりも低くなる可能性があります。
株式の贈与・分割でスムーズな承継
法人で資産を一元管理することで、相続時に「株式」として分割・贈与でき、トラブルを回避しやすくなります。
詳しいことは、また別のコラムでお話ができればと思います。
まとめ|資産管理法人設立は“目的に合った活用”がカギ
資産管理法人の設立は、賃貸オーナーにとって非常に有効な節税・相続対策です。
ただし、「節税できるから」という理由だけで設立してしまうと、
・コスト倒れ
・税務調査リスク
・法人運営の煩雑さ
に悩まされることになります。
設立前にやるべき3つのこと
1.現在の課税状況・収支を正確に把握する
2.10年単位でのライフプラン・相続設計を検討する
3.税理士・司法書士など専門家に相談し、スキームを設計する
おわりに|まずは「自分に合っているか?」を考えてみよう
資産管理法人は、節税だけでなく「資産を守り、次世代にどう渡すか」を考えるための手段でもあります。
決して万能薬ではありませんが、正しく設計し、正しく使えば強力な味方になることは間違いありません。
「自分も当てはまるかも…?」と思った方は、ぜひ一度、信頼できる税理士に相談してみてください。
将来の安心のために、“今”できる一歩を踏み出してみましょう。
私たち、資産パートナープランナーズも資産管理法人による節税対策の経験が豊富にありますので、ご興味のある方はお問合せください。



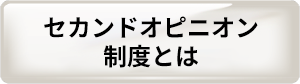
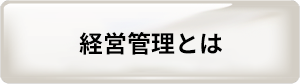
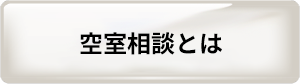

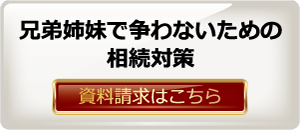
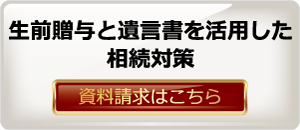
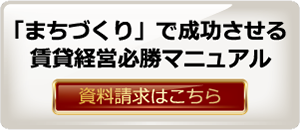
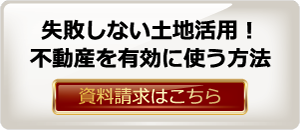




 所得税対策に有効な資産管理法人の設立とは?
所得税対策に有効な資産管理法人の設立とは?